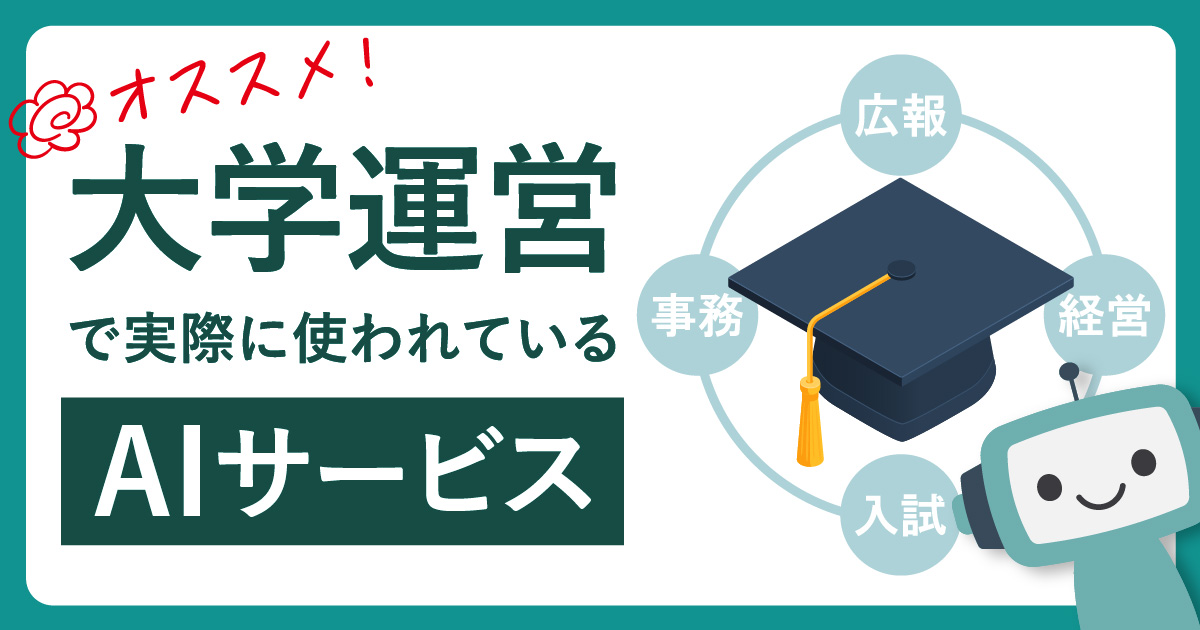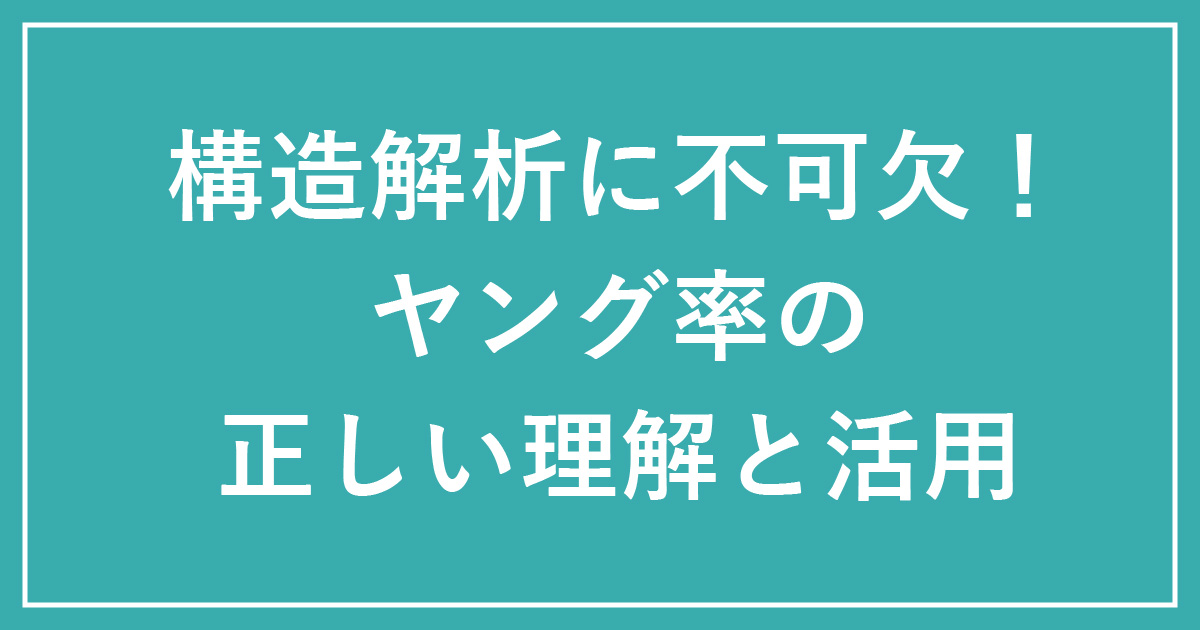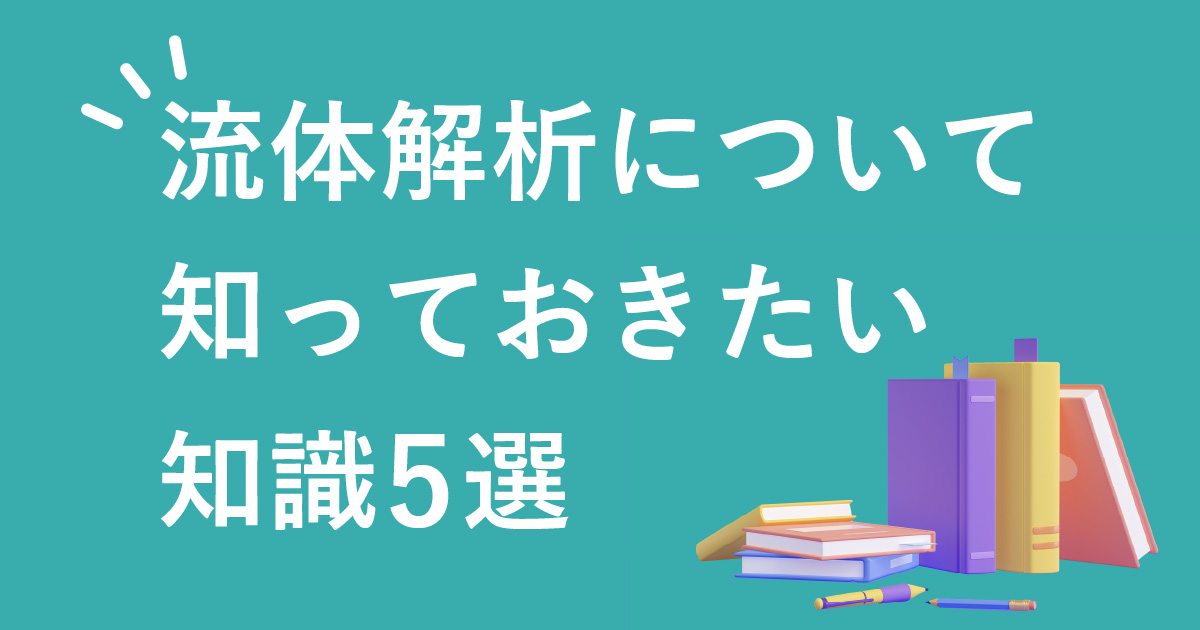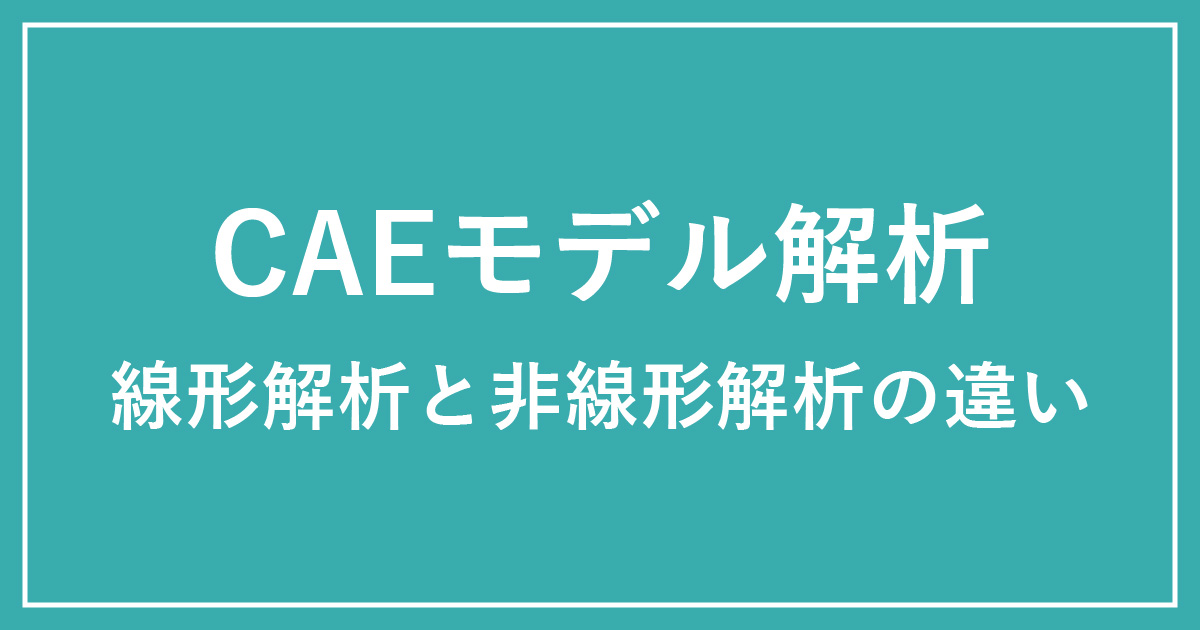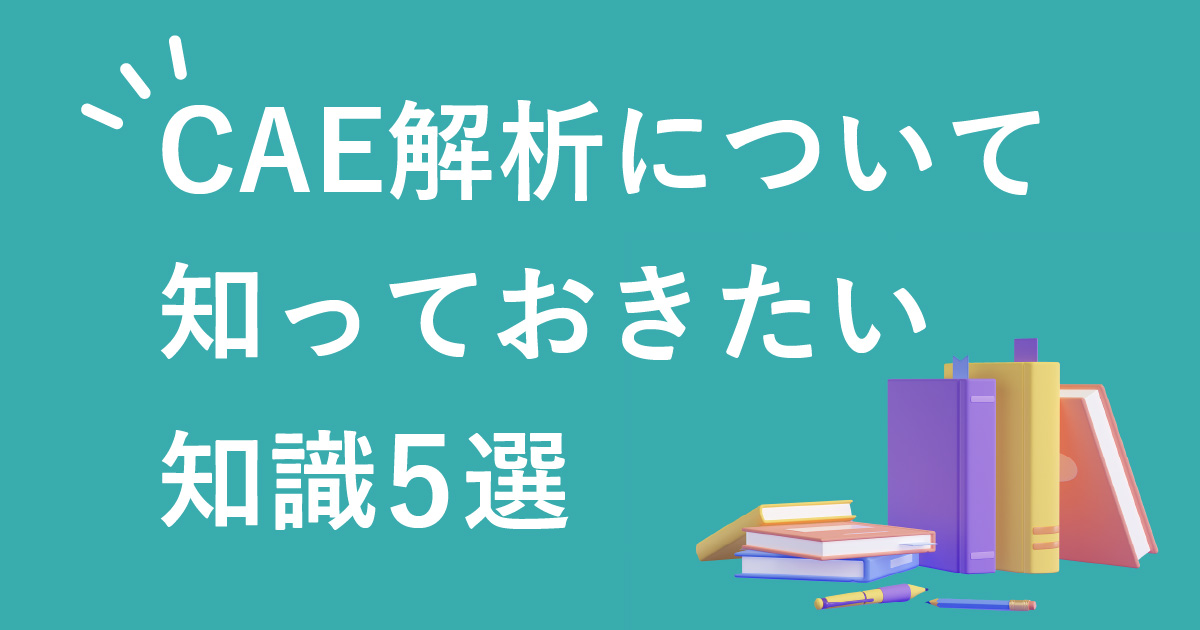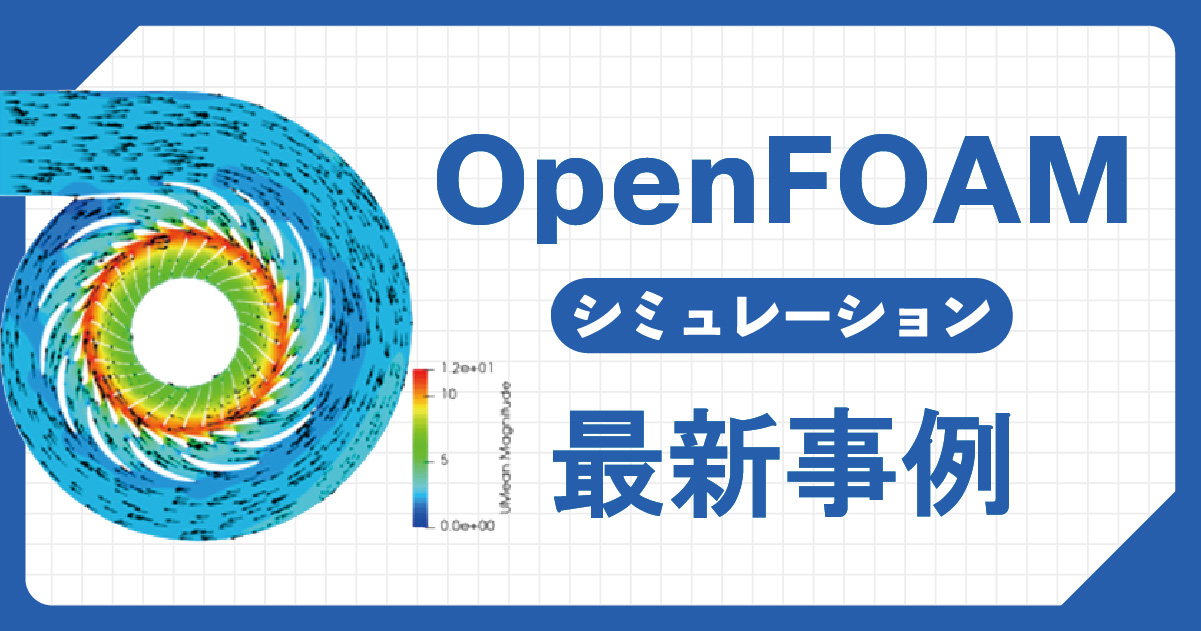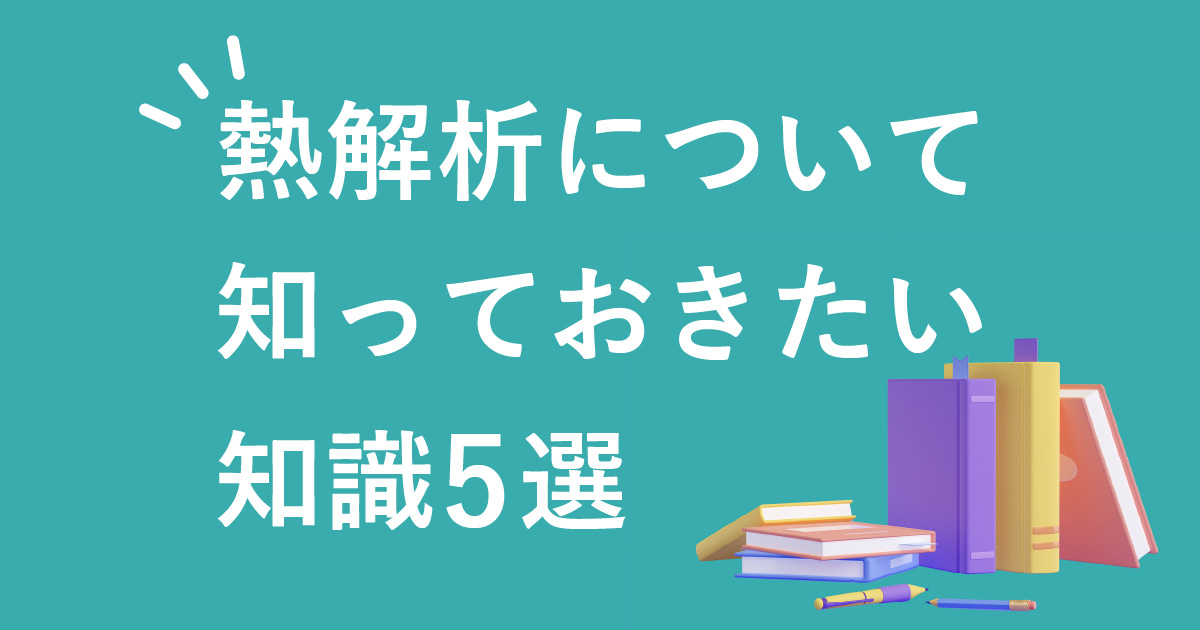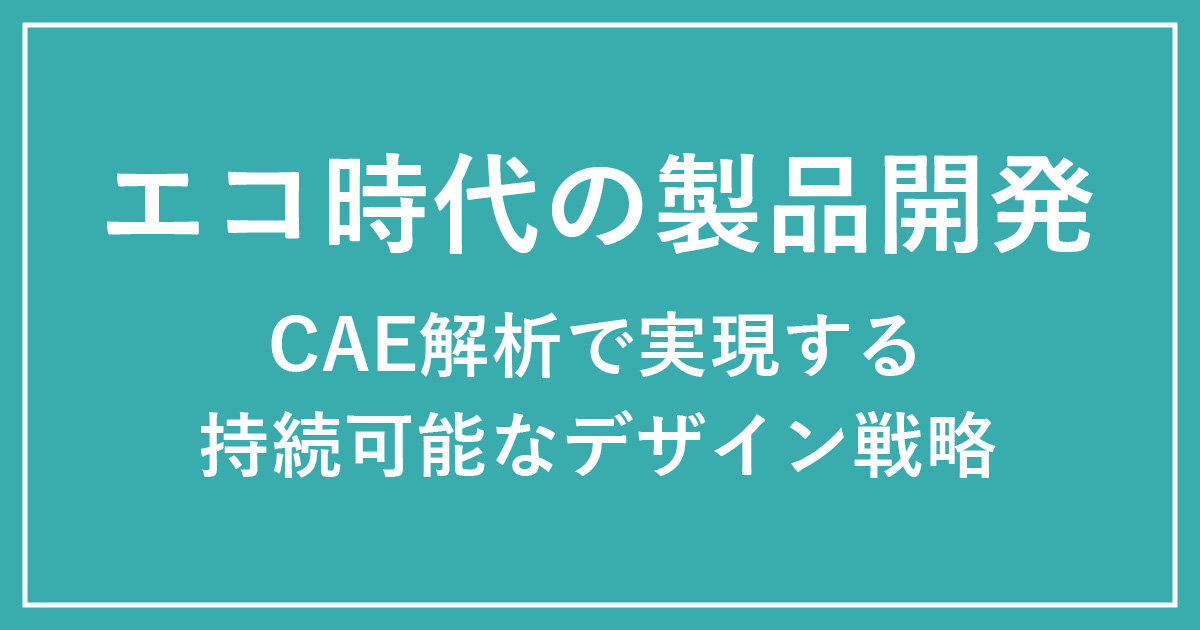【日本の大学×AI活用】全国26校の事例をまとめて徹底紹介

はじめに
生成AIやチャットボット、画像解析にいたるまで、AI技術は日々進化を続け、私たちの生活や働き方に大きな変化をもたらしています。
その波は高等教育機関にも及び、いまや多くの大学が、授業支援や業務効率化、学生サービスの向上といったさまざまな場面でAIを取り入れ始めています。
本記事では、全国26大学を対象に、実際に導入・活用されているAI活用事例を徹底的にリサーチ。
授業での応用から学生支援、職員業務の効率化まで、40件以上に及ぶリアルな実例を紹介します。
大学はAIとどう向き合い、どう活かしているのか?
これからの教育や大学運営のヒントとなる事例を大学別にまとめました!
目的別にAIサービスやツールを知りたい方は、こちらの記事をご覧ください ↓


大学・医療・研究機関で導入実績あり!
AIシステムの導入なら当社にお任せください
当社では、お客様にご希望に合わせたAIの開発を行っております
- 画像判定システム
- スタッフのシフト最適化システム
- お問い合わせチャットボット
- FAQ自動応答
- 学生×企業のマッチングシステム など
「何ができるのか知りたい」「まずは相談してみたい」など、お気軽にお問い合わせください
東北大学
全国初、ChatGPTを大学業務に本格導入
東北大学は2023年5月、全国の大学に先駆けてChatGPTを業務に導入。
事務・技術職員や教員を中心に約200人が利用し、文書作成やコードレビューなど幅広い業務を効率化しています。
特に、キーワードから複数の動画シナリオを生成する機能や、Google App Scriptの作成支援では顕著な効果を上げています。
従来必要だった知識や検索時間が不要となり、業務の生産性が大幅に向上しました。
学内チャットボットも生成AIで進化
2024年3月、東北大学は生成AIを組み込んだ新型チャットボットを導入。
従来のFAQ型から脱却し、独自の学内データをRAG(検索拡張生成)で読み込み、より柔軟かつ正確な応答が可能となりました。
多言語対応も強化され、外国人留学生や研究者の利便性も向上。
平均で2.7往復の対話が実現するなど、利用体験も大きく向上しています。
会議録要約アプリを内製開発
非テキストデータからの業務支援を目的に、動画・音声ファイルを文字起こしし、要約を生成するWebアプリを学内で開発。
AIの活用により、1時間の会議要約作成時間が従来の約1/4に短縮されました。
また、プロンプトの選択によって会議だけでなくインタビューの要約作成にも対応可能となり、広報業務への応用も進んでいます。
契約審査・翻訳・ナレーションにもAI導入
東北大学は早くからAIの業務利用に取り組み、2021年以降、契約書チェックの「リーガルフォース」や、音声翻訳の「オンヤク」、ナレーション作成に使える「ボイスピーク」なども導入。
生成AI登場以前から、多様な分野で業務の効率化・高度化を推進しており、現在の生成AI活用の土台を築いています。
京都大学
英語論文執筆支援にAIを導入し、研究力を強化
京都大学医学部附属病院では、研究者の働き方改革に伴い生じる「研究時間の確保」という課題に対応するため、AIを活用した英語論文執筆支援ツール「Paperpal™」を2024年10月より本格導入しました。
このツールは、英語の校正や翻訳を自動で行うもので、導入前に実施された試験運用では、8割以上の研究者から「作業の効率化に寄与した」「今後も使いたい」と高評価を獲得。
執筆の時間短縮により、研究活動そのものへより多くのリソースを割くことが可能になるほか、論文の質の向上も期待されています。
国際的な学術誌への掲載機会が増えることで、医療の現場への研究成果の還元スピードも加速すると見られています。
九州大学
医療現場に生成AI導入、DPC業務の精度と効率を両立
九州大学病院では、診療報酬制度であるDPC業務の支援に特化した生成AI「ユビー生成AI」の導入を2024年10月に試験的に開始し、2025年から本格的な検証に入りました。
診療録の情報から副傷病や処置内容を抽出し、コーディングを支援することで、事務スタッフの作業負担を軽減しつつ、報酬請求の正確性も向上。
業務の質とスピードの両立を目指すこの取り組みは、医療経営の最適化にもつながると期待されています。
「ユビーAI問診」で医療現場の問診を効率化
九州大学病院では、患者がスマートフォンやタブレットを使って問診を行える「ユビーAI問診」も導入されています。
このツールは問診内容を文章化し、病名の候補も提示。
医師はその結果をもとに電子カルテを効率的に作成できるため、事務作業を削減し、患者と向き合う時間を確保できます。
すでに全国1800以上の医療機関で導入されており、業務の質を高める手段として注目を集めています。
教育・学習支援でも生成AIの活用を推進
九州大学は教育分野においても生成AIの積極的な活用を進めており、「生成AIと教育・学習・業務」をテーマにしたFD・SDセミナーシリーズを継続的に実施。
授業設計の支援から、教員同士の事例共有、さらには学習支援チャットボット「MyAI」の活用まで、多面的な取り組みが行われています。
この内容は動画アーカイブとして公開され、学内外の関係者に活用されています。
大阪大学
国立大学最大規模、全学の事務部門に生成AI導入
大阪大学では、2024年5月に全学の事務部門約1,600名を対象に、生成AIサービス「Knowledge Stack」を導入。
GPT-3.5およびGPT-4を活用できる専用Azure環境を構築し、議事録作成や資料要約、文書翻訳、企画提案の支援など、幅広い業務での活用を目指しています。
閉域サーバでの運用により、情報セキュリティにも配慮。生成AIの力を借りて、職員の業務効率と創造性を同時に高めることを狙います。
医療の未来を形にする「AIホスピタル」構想
大阪大学医学部附属病院では、内閣府の「AIホスピタル」プロジェクトに採択され、病院内のさまざまな場面にAIを導入。
アバターによる手術説明や、音声入力による電子カルテ作成、自動運転車椅子など、医師や看護師の業務を支える実証実験が進行中です。
AIは単なる自動化ではなく、人の業務を拡張する「Augmented Intelligence」として捉えられており、患者との対話の時間を取り戻すことが最も大きな目的です。
北海道大学
入試改革に挑む「問いを評価するAI」
北海道大学では、「問いの力」に着目した入試改革に向けて、人工知能の導入を模索するユニークな研究プロジェクトが進行中です。
従来の「正解を評価する」方式から脱却し、「どんな問いを立てるか」を評価するAIの開発に取り組んでいます。
深層学習技術を応用し、人間の直感に近い判断を行えるAIを用いることで、受験生の思考の質や創造性を測ろうとする試みです。
将来的には、個別性や多様性に対応する“助言者”としてのAIの活用も見据えられており、教育とテクノロジーの融合に新たな可能性を示しています。
早稲田大学
早稲田大学、生成AIチャットボット「SELFBOT」を導入
早稲田大学は、在学生向け情報サイト「Support Anywhere」などに生成AI搭載のチャットボット「SELFBOT」を導入しました。従来の単語検索型と比べ、柔軟な回答生成が可能で、問い合わせ対応の精度と効率が大幅に向上。Slack上での活用も進められ、学生や教職員が日常のツール内で即座に必要な情報へアクセスできる環境整備が進んでいます。
神戸大学
AIが模擬患者に──神戸大学、医療面接トレーニングアプリを開発
神戸大学はフューチャー社と共同で、医学生向けにAIが模擬患者役を務める音声対話型トレーニングアプリを開発。
対面訓練の代替手段として、時間や場所にとらわれず学習可能な仕組みを提供しました。
自動評価と実写映像による臨場感ある学習環境により、教育の質向上と教員の負担軽減を目指しています。
千葉大学
研究支援に生成AIを導入「Web of Science Research Assistant」
千葉大学は、AI搭載の検索支援ツール「Web of Science Research Assistant」を導入。
研究者は自然言語での質問を通じて、Web of Scienceの膨大なデータから適切な回答を得られるようになり、文献検索の効率化が期待されています。
ChatGPTで文献スクリーニング時間を約9割削減
千葉大学とシンガポール大学の共同研究で、ChatGPTなどLLMを使った診療ガイドライン作成支援を実施。
従来17分かかっていた文献選別を約1.3分に短縮し、高い正確性も確認されました。
医療従事者の負担軽減に貢献する成果です。
立命館大学(立命館アジア太平洋大学含む)
英語学習にAIを導入、入試前教育として活用
立命館アジア太平洋大学(APU)は、AI英語学習システム「GET Test & Learning System」を、学校推薦型選抜の出願資格として初導入しました。
AIが受講者の英語力を分析し、個々に最適な学習カリキュラムを提供。
入学前の学習習慣を整え、大学でのスムーズな学びを促進する狙いがあります。
問い合わせ対応にAIチャットボットを導入し業務効率化
立命館大学とAPUは、学内の問い合わせ対応業務にAIチャットボット「BEDORE Conversation」を導入。
教務課や財務経理課などで電話・メール対応を削減し、教育DXを推進。
多言語対応や時差対応にも対応しており、教職員の業務負担軽減と情報提供の質向上を目指しています。
留学生入試にAIを活用、文章評価を定量化
APUでは外国人留学生の入試にAIを活用し、提出された文章の内容をAIが定量的に評価する仕組みを導入しました。評価のばらつきや人的負担の軽減に加え、多様な背景を持つ留学生に公平な審査環境を提供することが目的です。多国籍な学生が集うAPUならではの実践といえます。
熊本大学
ChatGPT搭載ロボット「ペッパー」を教育現場に導入
熊本大学は、ソフトバンクや熊本トヨタ自動車と連携し、生成AIを活用した教育・人材育成プロジェクトを開始しました。
対話型AI「ChatGPT」を搭載したヒト型ロボット「ペッパー」を導入し、附属小学校や特別支援学校での授業に活用。
子どもたちはAIとの対話やプログラミング体験を通じて、デジタル技術への理解を深め、未来の地域社会を担う人材の育成を目指します。
後半のページでは、残りの大学(上智大学や明治大学など)や、日本の大学のAI活用の特徴についてまとめています。